 PL/SQL
PL/SQL 【PL/SQL】仮想列(Virtual Column)とトリガーを使った自動整合設計
データの一貫性をアプリ任せにすると、更新漏れや整合崩れが必ず起きます。Oracleでは「仮想列(Virtual Column)」と「トリガー(Trigger)」を組み合わせることで、導出値や監査項目、正規化の補助列をデータベース側で自動生成...
 PL/SQL
PL/SQL 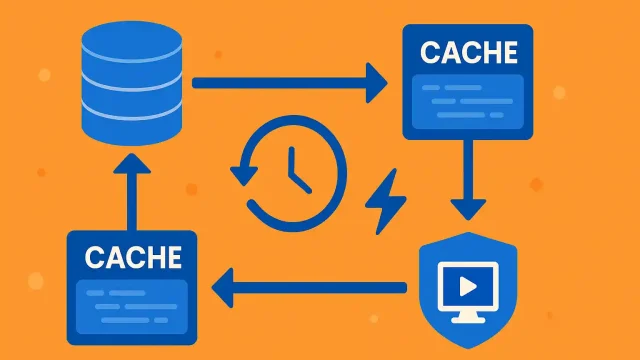 PL/SQL
PL/SQL  PL/SQL
PL/SQL  PL/SQL
PL/SQL 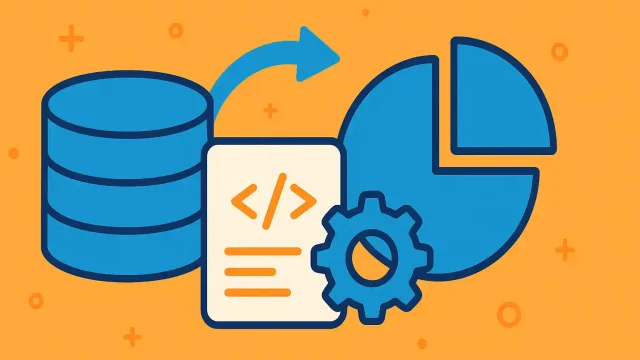 PL/SQL
PL/SQL  PL/SQL
PL/SQL  PL/SQL
PL/SQL  PL/SQL
PL/SQL  PL/SQL
PL/SQL  PL/SQL
PL/SQL 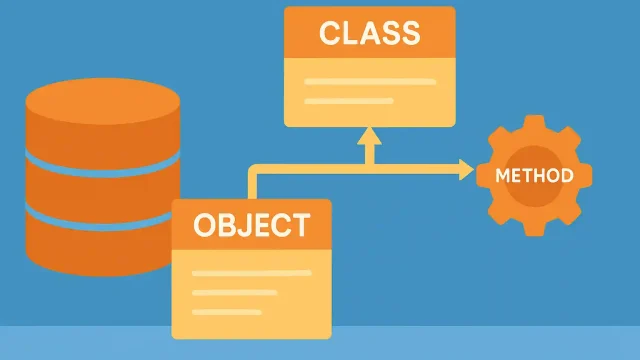 PL/SQL
PL/SQL 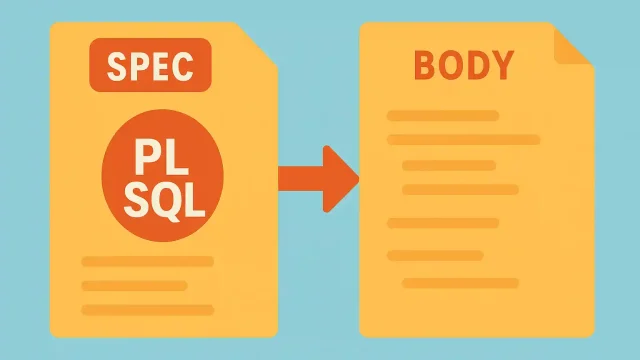 PL/SQL
PL/SQL 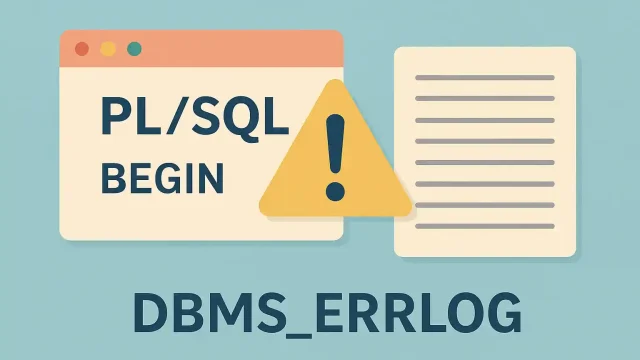 PL/SQL
PL/SQL 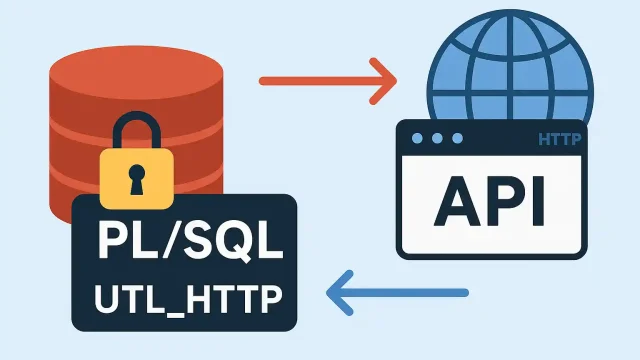 PL/SQL
PL/SQL  PL/SQL
PL/SQL 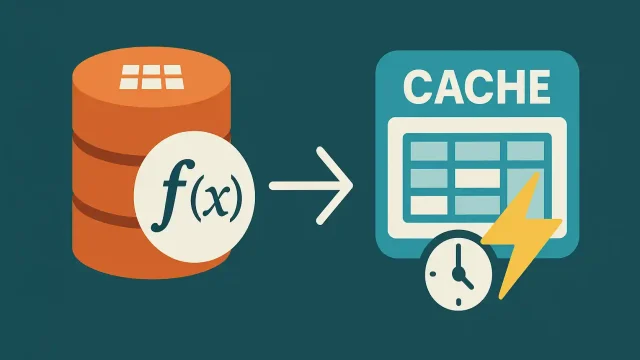 PL/SQL
PL/SQL 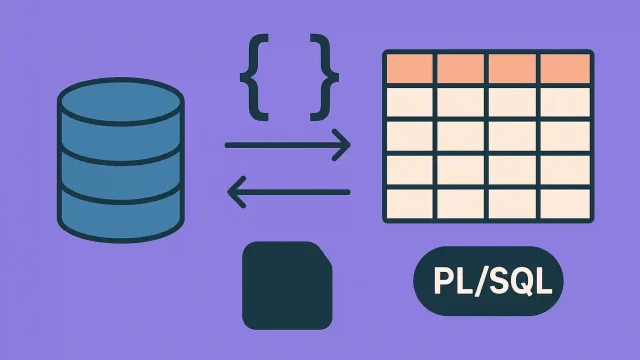 PL/SQL
PL/SQL 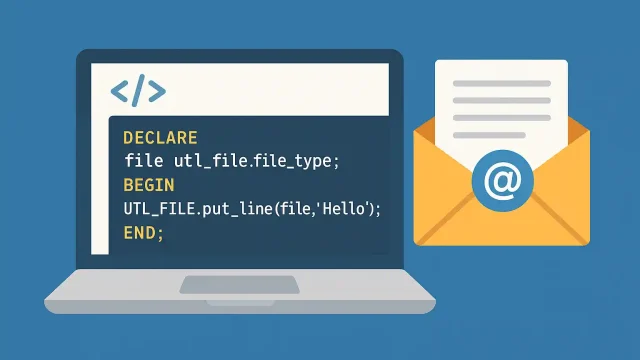 PL/SQL
PL/SQL 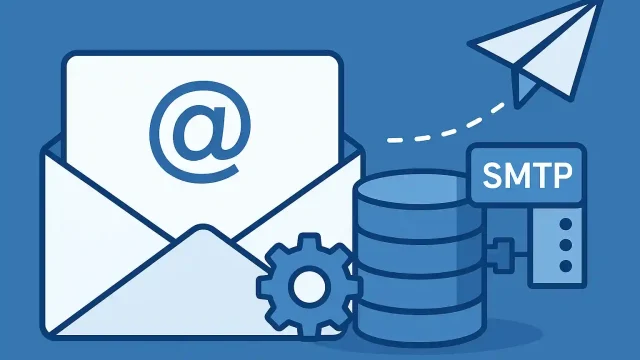 PL/SQL
PL/SQL  PL/SQL
PL/SQL